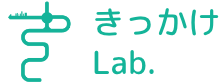勉強じゃなくても、脳はぐんぐん育つ
「うちの子、なにか習い事させた方がいいのかな?」
「ゲームや動画ばかりで、このままでいいの?」
そんな風に、子どもの“脳の育ち”について気になること、ありますよね。
でも実は──
子どもの脳は、“特別な教材”や“難しい勉強”じゃなくても、
日常の中で大きく育っているんです。
鍵になるのは、「好奇心」「感情」「体験」。
そして、親がそっと見守る“まなざし”です。
子どもの脳を育てる3つの“しかけ”
① 「なんで?」が生まれる体験
疑問は、脳を動かすスイッチ。
「どうして雨がふるの?」「なんで大人は働くの?」
そんな“なんで?”が浮かんだ瞬間、子どもの脳はフル回転。
親が全部答えを出さなくても大丈夫。
「どう思う?」「調べてみる?」と返してあげるだけで、
思考力・探究心・自立心が自然に育ちます。
② 五感と体を使うあそび
手でさわる、においをかぐ、音を出す、ぐちゃぐちゃにする。
そんな“感覚あそび”は、脳の発達と密接につながっています。
積み木、砂遊び、粘土、料理、木登り──
何かに夢中になる体験は、記憶力・空間認識・創造力など、
さまざまな脳の機能を刺激します。
③ “選ぶ”経験
選ぶことは、前頭前野(判断・思考の中枢)を動かす。
「今日はどっちの靴はく?」「先にお風呂かごはん、どっちにする?」
小さな“選択”を積み重ねることで、
子どもは「自分で決めた」という自信と、
自分の考えをもつ力を手に入れていきます。
非認知能力と脳の発達はつながっている
最近よく耳にする「非認知能力」。
これは、IQでは測れない“人として生きる力”です。
- 自己肯定感
- 協調性
- 意欲
- 忍耐力
これらは脳の“前頭前野”や“扁桃体”といった領域と関わっており、
感情を通じた学びや経験が鍵を握っています。
小学生くらいまでは、こうした力がぐんと伸びやすい“ゴールデンタイム”!
今日からできる、親としての関わり方
- 「どうだった?」より「なにが楽しかった?」を聞く
- 「正解はこれ!」ではなく「どう思った?」を大切にする
- 「だめ!」の前に「なんでそうしたの?」と聞いてみる
- 一緒に驚いて、一緒に笑う
どれも、特別な知識は必要ありません。
子どもの“感じたこと”に寄り添うだけで、
その脳と心は、ぐんぐん育っていきます。
“やってみたい”は、最高の脳刺激
子どもがふと発した「これ、やってみたい!」
そのひとことは、脳が「動きたい」と感じているサイン。
学びのきっかけは、勉強でも教材でもなく、
日常の中のちいさな驚きと、親のまなざしの中にあります。
今日も、子どもの「なんで?」に、
ちょっとだけ立ち止まって、耳をすませてみませんか?