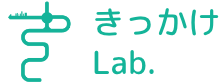「子どもの“考える力”や“心の強さ”、どう育てたらいいんだろう?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
テストでは測れない“生きる力”──それが、今注目されている「非認知能力」です。
この記事では、
📍 特別な教材がなくてもできる
📍 今日から実践できる “声かけ”や“関わり方”のヒント を紹介します。
日常のなかにこそ、子どもの“未来をつくる力”が育つ魔法があります。
🌱 非認知能力って、どう育てるの?
非認知能力は、特別な授業や教材ではなく、日常の中の“ちょっとした関わり”で育っていくものです。
子どもが失敗したとき、挑戦したとき、悩んでいるとき──
その瞬間にどう声をかけるか、どんな関わり方をするかで、「自分で考える力」「人とつながる力」「感情をコントロールする力」などが、少しずつ育まれていきます。
非認知能力はすぐに結果が見えるものではありませんが、大人との“あたたかい関係性”や“信じてもらえる体験”の積み重ねが、子どもの内面に確かな土台をつくっていきます。
🗣 声かけのヒント|“結果”より“気持ち”や“過程”に目を向ける
私たちはつい、結果に反応してしまいがちです。
でも非認知能力を育てたいなら、子どもがその行動のなかで「何を感じたか」「どんなふうに考えたか」に注目することが大切です。
たとえば…
- 「100点すごいね!」→「難しいところ、どうやって工夫したの?」
- 「できた?」→「やってみて、どんな気持ちだった?」
- 「失敗しちゃったね」→「どこがむずかしかった?次はどうしたい?」
✅ ポイントは、「評価」ではなく「内面への共感」。
子どもが自分の中にある“気づき”に耳をすませることができるよう、言葉を選びましょう。
🤝 関わり方のヒント|“安心できる場”が、挑戦を育てる
非認知能力が育つには、「失敗しても大丈夫」「ここなら安心して自分でいていい」と思える環境が必要です。
- 間違えても、すぐに正さない。「どうしてそう考えたの?」と興味を持って寄り添う
- イライラしたときは、感情を否定せず、「どんな気持ち?」「ことばにしてみようか」と手渡す
- 子どもが言葉にできない気持ちに、「〜って感じかな?」と大人がラベルを貼ってあげる
✅ ポイントは、「感情の安全基地」になること。
どんな気持ちでも受けとめてくれる大人の存在が、挑戦のエネルギーになります。
🛠 こんな場面で実践してみよう
いつもの日常に、非認知能力を育てる“ヒント”はあふれています。
ちょっとした会話や関わりの中で、子どもが「感じる・考える・選ぶ」きっかけをつくってみましょう。
🎨 絵を描いたあと
つい「上手だね」で終わらせていませんか?
- 「なにを思いながら描いたの?」
- 「色はどうしてこれを選んだの?」
- 「ここ、すごく工夫してるね!」
➡ 子どもが“自分の中の選択”に気づくことができます。
⚽ 練習試合の帰り道
うまくいったときも、いかなかったときも、心が動いているはず。
- 「今日、一番楽しかったのはどこ?」
- 「悔しかったことってある?」
- 「次はどうしたいって思った?」
➡ 感情の整理と、自己理解のサポートにつながります。
🧩 失敗したとき
失敗は「責める」ではなく、「育てる」チャンス。
- 「うまくいかなかったね。どうしてそうしたのか教えてくれる?」
- 「もう一度やるとしたら、どうする?」
➡ “結果”ではなく“思考の過程”に光をあてましょう。
🍳 家のお手伝いのあと
たとえ不器用でも「関わったこと」に目を向けて。
- 「ありがとう、どんなことを意識してくれたの?」
- 「ここ、すごくていねいだったね!」
➡ 自信と主体性が育ちます。
✅ ポイント:どの場面でも「すぐにアドバイスしない」「正しさで評価しない」
子どもの中にある“芽”を一緒に見つけ、育てるような言葉がけを意識しましょう。
✨日常こそが、“育ちのステージ”
非認知能力は、特別なことをしなくても、毎日の中で少しずつ育てていけます。
親子の会話、遊びの時間、ちょっとした失敗──それらがすべて、学びと成長のチャンスです。
子どもが自分の力で考え、感じ、選びとるための“心の土台”を、今日の関わりのなかから、育てていきましょう。