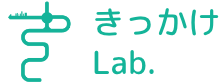「きっかけ Lab.って、何をしている会社なんですか?」
そんなふうに聞かれることが、よくあります。
けれど、実はそれをひと言で説明するのは少し難しいのです。
なぜなら、私たちは“何をするか”よりも、“なぜそれをするのか”を大切にしているから。
誰もが、自分の心にそっと耳をすませて、
「こっちに進んでみたい」と、自分で選び取っていける未来。
そんな社会をつくりたいという願いから、私は「きっかけ Lab.」を始めました。
「きっかけ」にこだわるようになった理由
今となっては、それがとても特別だったのだと思います。
幼いころから、英会話、学習教室、水泳、サッカー、ピアノ、陸上競技…
本当にたくさんのことにチャレンジさせてもらい、
生徒会やスポーツの全国大会、留学など、
経験という“きっかけ”を積み重ねながら育ちました。
けれど、それがどれほど恵まれた環境だったかに気づいたのは、20歳を過ぎてからのことでした。
「できる・できない」ではなく、「やってみたい」と思ったことを
選べること自体が、どれほど貴重なことだったか。
そう気づいたとき、私は思いました。
「誰にでも、選べる材料があっていいはずだ」と。
「10代で未来なんて、決められない」
進路に迷った高校時代。
サッカーを断念し、人生で初めて“夢が空白になる瞬間”を経験しました。
そんなとき、自分を動かしたのは「経験」でした。
体験したことしか、心から“自分の言葉”にはできない。
それが、私なりの答えでした。
そしてもう一つ、ずっと抱いていた違和感。
文理選択、進学先、将来の職業――
日本の教育は、10代のうちに“人生を決めること”を求めすぎているのではないか?
正解を選ぶことよりも、選びながら考え、自分のペースで育っていけるほうが
よっぽど豊かではないか。
アメリカの大学のように、進学後に専攻を選べる柔軟さがあってもいい。
もっと「迷える時間」や「選び直せる道」があっていい。
それこそが、“自分で未来を描く力”につながっていくと、私は思っています。
「子どもと社会を、もっと近くに」
探究学習やキャリア教育の現場に関わる中で、
私はずっと、“社会”が遠くにあるような感覚を抱いていました。
大人たちは、子どもたちを「まだ何も知らない存在」と思い、
子どもたちは、社会のリアルを知らないまま「大人のマネごと」をさせられている。
でも、本当は社会は“遠い世界”なんかじゃなくて、
子どもたちのすぐそばにあるもの。
そして、大人たちも「育てる側」ではなく、
「ともに学び合う存在」であってほしい。
Exploreというプロジェクトを通して、
子どもと社会のあいだにある“境界線”を、やさしく溶かしていきたい。
私はそう考えています。
「心に向き合うことは、余白をもつこと」
誰かと話す。深呼吸する。空を見上げる。
それだけで、涙が出そうになる日が、確かにありました。
がむしゃらに頑張りすぎて、
気づけば空を見上げる時間も、心の声に耳をすませる時間もなくなっていた。
「立ち止まること」に、罪悪感すら感じていた自分がいました。
でも、本当に大事なのは“心”でした。
一度立ち止まって、自分の気持ちを見つめ直して、整える。
その先にしか、「本当に行きたい場所」なんて見えてこないのだと思います。
Balanceというプロジェクトは、そんな“心の余白”を取り戻すための挑戦。
誰もが、自分の心にやさしくできる社会へ。
私は、そう願っています。
「気づく」から「ときめく」、そして「踏み出す」へ
「こうしたい」という自分の気持ちを、
誰かの言葉に頼るのではなく、
自分自身の体験や想いから描いていけるように。
未来につながる“きっかけの種”を、そっと寄り添いながら、今日もまいていきます。
「きっかけノート」では、
心が少しだけ動いた瞬間を、これから少しずつ綴っていこうと思います。
またのぞいてもらえたら、うれしいです。